〜あなたの金融の悩み、本当に「正しい常識」で解決していますか?〜
「投資は怖い」「手数料が高いのは分かっているけど、長年の付き合いだから地方銀行がいい」「ペイオフのために資産を分散すべき?」—こうした疑問や感情は、資産形成を進める上で多くの人が抱えるものです。
しかし、これらの「常識」や「感情的なこだわり」が、あなたの合理的な資産拡大を妨げているかもしれません。
「ペイオフ対策」は無意味?1000万円分散が不要な金融機関破綻の真実
<ペイオフ制度の「理屈上の意味のなさ」>

皆さんの中には、「ペイオフのために1000万円単位で資産を分割した方が良いのではないか」と考え、その資金を「何かあった時の元本保証枠」として検討している方はいませんか?
ペイオフとは、金融機関が破綻した場合に預金者の預金が1000万円まで保護される制度です。
しかし、専門家は「このペイオフという制度、本当に意味あんの?」という疑問を投げかけます。その理由は、金融機関が顧客の資産を分別管理しているからです。
分別管理とは、銀行が経営に使う資金と、顧客から預かっているお金を別々に管理しているということです。
銀行が倒産(破産)するのは、経営資金などがなくなった時であり、顧客の預金口座のお金がなくなるわけではありません。そのため、理屈上、銀行が破産したとしても、顧客のお金は残るはずなのです。
<過去の事例と大口資産家の行動>



過去50年間で、実際にペイオフが発動した事例は一度もありません。
• 足利銀行の経営破綻:この事例では、国が銀行ごと国有化(国が買収)し、預金者は完全に保護されました。
• 山一証券の倒産:山一証券の破産により、その口座を持っていた人が損をしたわけではありません。当時、世の中が不景気になり、投資家全体が株を売った結果、株価が下落し資産が減ったという話です。山一証券における顧客のお金がなくなったわけではありません。



また、仮にペイオフ対策が必須なら、2000億円ほどの資産を持つ人物(例えば、前澤氏)は、2万個もの銀行口座が必要になってしまいます。
しかし、実際にはそのような大口資産家が2万個も口座を持たないことからも、ペイオフ対策は無意味であるという現実が示唆されます。
地方銀行への「親しみ」があなたの資産を減らす理由



長年取引があり、「親しみのある」地方銀行の口座を、手数料が高めでも活用する方法はないか、という質問に対して、私はは厳しい現実を伝えています。
<銀行にとって本当に大切な顧客とは?>
顧客側が「私は500万円も預金しているのに」と考える一方で、銀行側は必ずしも一般の預金者をそこまで大切に思っていません。
銀行にとって大切な顧客とは、地主、資産家、企業、そしてローンを組んでいる人です。銀行は、お金を貸すことで利益を得るため、預金があること(預金残高)はぶっちゃけどうでもいい、というのが本音であり、顧客との間に「ズレ」が生じているのです。
<地方銀行での投資は非合理的な選択>



地方銀行の担当者自身も、楽天証券やSBI証券などネット証券と比べて、自社の投資信託の手数料が高いことを認識しています。
特別なメリットがない限り、「親しみがある」という理由だけで手数料の高い地方銀行との取引を続けると、結果的に傷つくのは自分であり、合理的な判断とは言えません。
生命保険の「情」による解約の遅れ
友達や親戚から加入した生命保険を「解約すると相手に迷惑がかかるかも」とためらう人もいますが、多くの場合、加入から3年以上経過していれば、解約しても募集人にペナルティ(報酬の一部返納)は発生しません。気にしているのは自分だけで、相手はそこまで気にしていない、という例は金融の世界ではよくあるのです。
NISAを最強の節税ツールに変える!「贈与後の運用」戦略シミュレーション



余剰資金を大学生の息子(子供)のNISA枠で投資すべきか、という質問に対し、私は「理屈上、先に資金を贈与した方が得である」と断言しています。
これは、**「運用後の贈与」と「贈与後の運用」**を比較した結果です。
<圧倒的に有利な「贈与後の運用」>
どうせ親から子供にお金を渡す(贈与する)のであれば、運用によって資産が増えた後に贈与するよりも、先に贈与して子供に運用させた方が、長期的に見てはるかに効果が大きいのです。



具体的なシミュレーション(年利5%、20年間運用)を見てみましょう。
| シミュレーションケース | 親が運用後、子に贈与 | 子に贈与後、子が運用(NISA利用) |
| 元本 | 400万円 | 400万円 |
| 運用期間 | 20年間 | 20年間 |
| 20年後の金額 | 1,061万円 | 973万円 (※) |
| 最終的な受取額 | 866万円 (贈与税195万円控除後) | 973万円 (贈与税33万円支払い後、367万円運用) |
| 最終的な差 | – | 約107万円多く受取可能 |
※注:贈与税を先に支払うため、実際の運用元本は367万円となる。NISA枠(非課税)で運用するため、運用益に対して税金はかかりません。
このシミュレーションが示すように、先に贈与税を支払い、子供の非課税枠(NISA)で運用させる方が、最終的な受取額が100万円以上多くなるという結果になりました。いつか子供に渡す前提の資金であれば、先に贈与してしまう戦略が、長期的な資産形成において圧倒的に有効です。
投資は怖い人を変える方法:馬に水を飲ませる難しさ



40代の姪にNISAを勧めても「投資は怖い」と消極的である、という相談に対し、私は「ぶっちゃけ他人を変えることは難しい」と現実的な見解を示しています。
<お金への関心は年齢とともに高まる>
実は、日本で最もお金に関心があるのは、50代や60代とされています。この年代になると、退職が近づいたり、健康の不安が増したりすることで、「やはりお金が大切だ」と危機感を持ち始めるからです。
一方で、20代、30代、40代といった若年層は、「いつか何とかなるだろう」と考えたり、まだ危機感が薄かったりする傾向があります。これは仕方のない側面もある、とされています。
「馬を水辺に連れて行くことはできるが、水を飲むかどうかは馬次第だ」ということわざがあるように、アドバイスはできても、相手が行動するかどうかは相手次第なのです。



もし大切な人に寄り添いたいのであれば、今は関心がない人に何を言っても響かないため、相手が自発的に危機感を持つ時まで見守り、相談に乗れる関係性を維持しておくことが、最も現実的なアドバイスとなります。
80代の資産運用戦略:増やすことよりも大切な「目的意識」



友人の80代の母親が、大手銀行で増えないバランス型ファンドを多数購入している件について、売却後の運用先(投信、債券、定期預金など)についてのアドバイスを求められたことがました。
<80代の投資は「取り崩しステージ」>
まず考えるべきは、80代における投資目的です。80代は、一般的に「取り崩しを始めているステージ」であり、これから急激にお金を増やし続ける必要性は薄いかもしれません。
最も大切なのは、「このお金が一体何のために使われるのか」という目的意識です。
<目的別に見る合理的な選択肢>
1. 元本保証・安定性重視の場合(何かあった時のための資金)
S&P500などの株式はアップダウンが激しく、必要な時に元本より増えている保証はありません。この目的であれば、何だかんだ言って現金や定期預金が良い選択肢となります。
2. 相続前提の場合(使わない可能性が高い余剰資金)
どうせ使わず相続される可能性が高いのであれば、以下の合理的な選択肢が提案されています。
◦ 一時払い終身保険: 合理的な対策の一つとして挙げられます。
◦ 株式運用: 相続を前提として、S&P500や全世界株式など、ボラティリティ(変動)があるものの、運用を続ける。



資金の一部を使って残りを一時払い終身保険とS&P500などに分割して運用する併用も可能です。
「よくわからないけど銀行よりは増えるから」という曖昧な理由で投資を行うのが最も避けるべき行為です。何に投資をするかではなく、「このお金は何の目的で必要なのか」という逆算的な思考が、最適な手法を導き出す鍵となります。
投資を成功させる最大の鍵は「目的意識」



本記事で解説したように、金融の世界では、感情や長年の慣習、非合理的な思い込みが、あなたの資産形成を阻害することがあります。
ペイオフ対策は理屈上無意味であり、地方銀行への「親しみ」は手数料というコストとして跳ね返ってきます。
一方、NISAと贈与を組み合わせた「贈与後の運用」戦略のように、理屈に基づいた合理的な行動は、最終的に100万円単位で資産に差を生み出します。
そして、あらゆる投資行動において重要なのは、**「このお金は何の目的で必要なのか」**という目的意識です。あなたの資産が、その目的に沿って最も効果的に機能するよう、感情ではなく、常に合理的な判断基準を持つことが、資産拡大への近道となるでしょう。


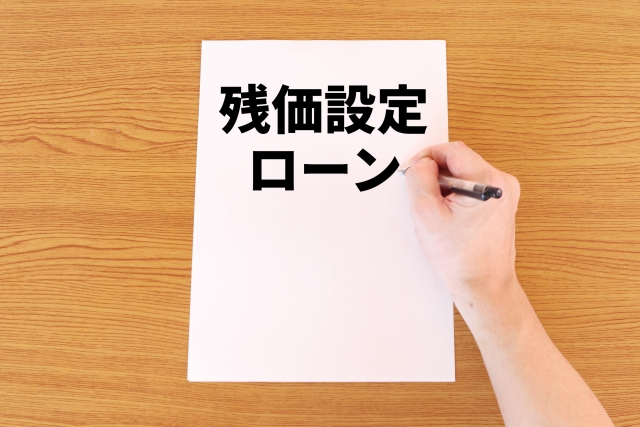


コメント